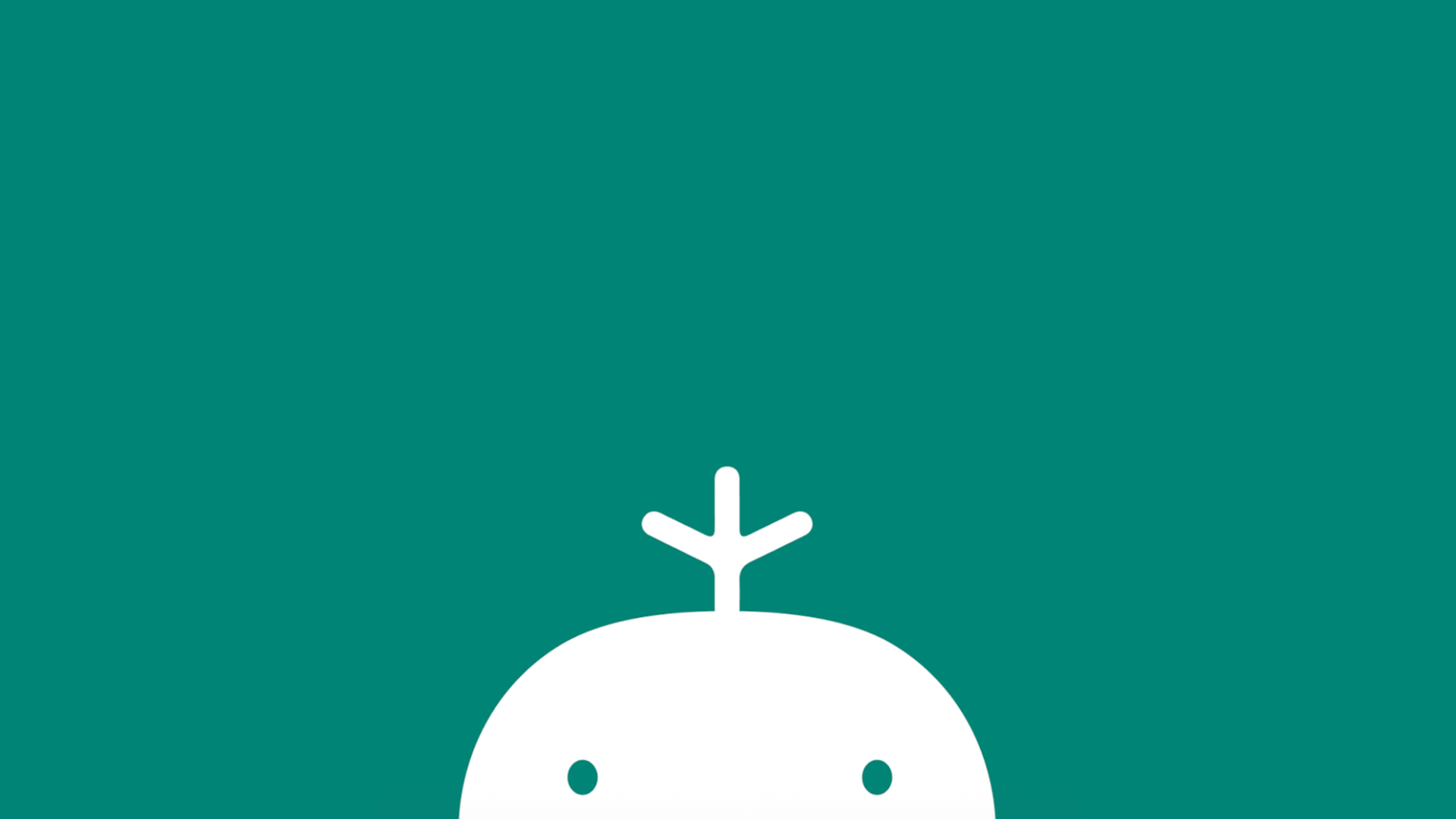言葉で人をつなぎ、意見という名の「種」をまく
キニマンス塚本ニキインタビュー(2/2)

進行・構成:POLYGLOTS magazine編集部 写真:Coco Taniya
意見の表明は「種まき」
通訳のキャリアと並行して、2020年からラジオパーソナリティを始め、各メディアで発言されることも増えていきます。先ほど、幼少期は「空気を読む」タイプだったとおっしゃっていましたが、今のニキさんの活動や発言からは、社会的な議論を起こすために、意図的に「空気を読まない」ことをされている、と感じることもあります。その変化にはどのような経緯があったのでしょうか。
そうですね。日本に戻ってきた23歳当時って、「日本に喧嘩売りに戻ってきたぜ」みたいな意気込みだったかもしれないです(笑)。私自身は日本がすごく好きで、 9歳でニュージーランドに移るときは、「日本を離れたくない!」って泣きながら飛行機に乗るぐらいでしたし、お正月に戻るたびに「やっぱ日本最高!」って思ってたんですけど、高校生ぐらいになって、どうやら日本はずっと不況が続いているらしいとか、凶悪犯罪が増えているらしいとか、閉塞感が漂っているらしいとか聞くけど、テレビをつけると「日本の未来は世界が羨む!」ってキラキラしたアイドルの女の子たちが歌っていたりして。お年玉を全部使っちゃうぐらいアニメや漫画などの日本のポップカルチャーが大好きだったんですけど、だんだんと「娯楽が娯楽すぎる」というか、「みんな現実から目を背けたくてコレに夢中になっているのでは?」と違和感を覚えるようになったんです。それが2000年前後ですね。その時はうまく言語化できなかったけど。
日本でいう高校3年生の年にイラク戦争が始まって「え、なんか世界やばいじゃん」と徐々に思うようになったわけですが、ニュージーランドの友達と「ブッシュ、マジムカつくよね」って、表面的な内容も多かっただろうけど、話題にはしていました。でも大人になって日本人の友達とそれをやるとなぜか気まずくなることが多々あって。そこから日本の社会意識や社会課題をもっと知りたいと思うようになったんです。「どうした日本!」と喝を入れてやろう、みたいな。実績も資格もまったくないのに威勢だけいい状態で戻ってきました(笑)。
日本で社会や政治の話、国際問題の話がなかなかできないという背景には、議論しても何も変わらないのではないかという無力感や、意見が衝突して親しい人との良好な関係が壊れてしまうのが怖いという感覚があるのかもしれません。
私も無力感や恐怖心はあったけど、それよりも「みんなが問題を知ろうとしないから変わらないんじゃないか」ってずっと怒りみたいなものを持ってました。でもあるとき、他人は変えられないけど、自分の思考や行動だけは間違いなく自分で選べるんだと気づいて。だから少なくとも「私は」環境破壊や児童労働との関連が指摘されている企業の商品を買わないという選択をして、支持や反対をちゃんと意思表明したいって思うようになりました。
「あの子、なんかクセ強いよね」って思われないことを第一に優先するのか、それとも自分の気持ちや価値観を尊重して守りたいのかって考えたら、やっぱり自分がおかしいと思うことをおかしいってちゃんと言っても大丈夫でありたいと思ったんです。それをリスペクトしてくれる友達が欲しいし、それで離れていく人がいたらそれはしょうがないかなと。
それで、「ゴミはゴミ箱に!」みたいな当たり前のことから、「このメーカーの商品は動物実験しているから買わない!」と啓蒙活動みたいなことまで、気心の知れた友達に話したり、SNSで発信していたら、何年も経ってから「あ、そういえば私、ニキが以前言っていたあの洗剤をやめて、エシカルな商品に変えたんだよ」って言われたりして。そのとき、「自分は“種まき”をしてたんだな」って気づいたんです。

「種まき」という感覚は素敵ですね。いきなり誰かと正面からぶつからなくてもできることですよね。
即効性はないしコスパもあまり良くないんですけどね(笑)。人前で社会的な意見を表明するのが難しければ、何かメッセージ性のある小さなバッジをつけるとかでもいいと思うんです。街角やお店ですれ違った人と「あ、そのバッジって・・・」というコミュニケーションが生まれるかもしれない。私もそんな形で友達になった人、何人かいますよ。
ラジオ番組『アシタノカレッジ』や、ご著書の『世界をちょっとよくするために知っておきたい英語100』(以下「せかよく」)もそういった「種まき活動」の一環だと思いますが、ラジオや本で、いま世界で議論されていることや、どんどん生まれる新しい概念を日本に紹介する、というニキさんの最近の活動の背景にはどのようなモチベーションがあるのでしょうか。
ひとつはすごく利己的な理由なんですが、私が日本でラジオをやらせてもらったり、 SNSで議論したりするときの発信は完全に日本語なわけですが、発信者ではなく一個人として、英語圏インターネットの話題を英語話者の友達と話して盛り上がることもあります。そういうことをすぐに日本語に直訳できなかったり、英語圏のすごくユニークな社会風刺コンテンツやミームを日本の友達に「見て、これ面白いよ」って気軽に共有できないっていうのがちょこちょこあって。言葉ひとつ言うだけで、その意味だけでなく、その言葉の背景まで全部説明しなきゃいけなくなっちゃうっていう。そこで、私が関心を持っている色々な言葉が日本語でも理解されるようになってほしいって思ったのがきっかけですね。
「せかよく」の読者の方から「知らない言葉がいっぱいあって勉強になりました」って言われるとすごく嬉しいんですけど、「いまさら聞けない英語!」とか「当たり前の新常識!」とかそういう上から目線のものでは決してなくて、「こういうイシューがもしかしたら日本でも潜在的にあるかもしれないけど、これについてあなたは思うことある?」みたいに、考えることを促す本であるといいなって思ってます。英語学習の本の体ですが、この本で英語が上手くなるとかは、二の次かもしれないですね。

ちょっと突っ込んだ話になってしまうかもしれないのですが、こういった「海外でこういう価値観があるよ」という紹介が、欧米中心的な視線である、みたいな批判があるとしたら、そこについてはどう思われますか。
例えばこの本にも書きましたが「decolonization」(脱植民地化)という言葉なんかは、歴史的に植民地支配という加害を行ってきた国々の人達が、「自分たちの国がこんなに豊かなのは奴隷制度や植民地支配の上に経済を成り立たせていたからだ」 と、自国の歴史を再認識し、その影響が現代にどう続いているのかを考えるきっかけになっています。一方で、発展途上国と呼ばれる国の人々や、社会の周縁に追いやられた先住民などの人々にとっては、「私たちの地域が貧しくて不安定なのは何百年にもわたる宗主国の支配や搾取が今も影響しているからなんだ」という目線から、自分たちの文化の価値や強みを再認識するというムーブメントにつながっています。「植民地支配」という負のレガシーから現状をどう立て直すのか、その責任は誰にあるのかっていう議論は西洋諸国に留まらず、学問の場からSNSまで、世界各地で活発に繰り広げられているんですよね。あくまでこの本はそういうことを知る「入口」になればいいなって思っています。
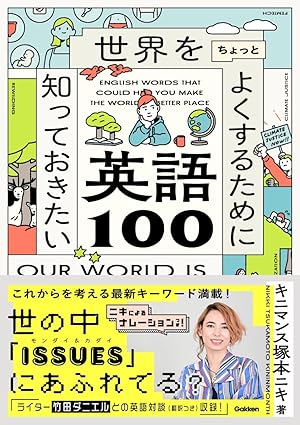
世界をちょっとよくするために知っておきたい英語100
ニキさん初の著書。定価 1,870円(税込)Gakken
違いを認め合うための「英語」と「自己表現」
ありがとうございます。最近気になっているワードはありますか。
ジェンダーの話につながるワードなんですが最近、「bro」(ブロ)に関連する言葉が多岐にわたって面白いなと思っていて。「bro」っていうのは「brother」のことで「アニキ」、「〇〇ニキ」みたいな言葉ですが、一部の男性カルチャーのマチズモを暗に批判するニュアンスが混ざっているんですね。例えばシリコンバレーをはじめとするIT企業文化で、「ガンガン稼いでいくぜ!」「第二のザッカーバーグ目指すぜ!」みたいな男性たちの馴れ合いコミュニティにいる起業家たちは「tech bros」(テックブロ)と呼ばれています。実際、テック業界のトップに君臨する男性たちがトランプ大統領と密な関係になっている現状が問題視されたことから、oligarachy(オリガルヒ、寡頭制)とbroをかけた「broligarachy」(ブロリガーキー。少数の裕福な男性たちが政治を動かすこと)なんて言葉も去年の大統領選挙の頃から広まり、すでに市民権を得ているんです。
先のアメリカ大統領就任式にテック界の大物たちが列席した光景は記憶に新しいですが、それがすでに言語化されていたんですね。
ほんと、言葉って次から次へと生まれてますよね。あとはこれはウェルネスとかメンタルヘルス、子育ての文脈ですがThe Guardian(イギリスの新聞、ウェブメディア)で読んだ「touched out」(「触られ疲れ」のような意味)っていう言葉も気になりました。
子育てする中で主に母親が甘えん坊な子供にベタベタと触られ続けることがストレスになってしまう状態を「touched out」って言うそうなんです。ワンオペ育児の限界みたいな話にも繋がるんですけど。子供を愛してるけど、もう自分の体が自分のものではなくなってしまうぐらい常に触られて、自分の体を尊重されてない気持ちがする。でも、子供は幼いからしょうがない。でも、この苦しみをどうしたらいいの、っていう感覚を言語化した言葉です。
この概念をママインフルエンサーが「私はいまこんな状態なんです」ってSNSでシェアして、それを見た当事者が「ああ、それ私も同じだ」って気づいて、”It’s OK if you feel touched out.”(touched outな気持ちになっても自分を責めないで)とか “It’s OK to protect your personal space.”(自分のパーソナルスペースを守っていいんだよ)みたいに共感の輪が広がって行く。そこから子育て世代のメンタルヘルスについて考えよう、とか、どうしたらこれほど余裕のない育児を社会全体で変えられるのか・・・という議論にもつながっていく、みたいな流れです。
あとは「せかよく」にも書いた「digital immortality」(デジタル不老不死。AIで故人のアバターを作るなど、テクノロジーを使って人の死というものを乗り越えること)関連にも興味があります。これは残された人にとってはgrief care(喪失体験のケア)の一環になるかもしれないし、不健全な形で依存させてしまうかもしれない。日常の思考整理やカウンセリング代わりとしてAIに頼る人は特にこれから直面するイシューになると思います。
最近、アメリカで煽り運転がきっかけで射殺されてしまった男性の遺族が、被害者の生前の映像を使ってAIで作ったvictim impact statement(被害者影響報告書。犯罪被害者が受けた影響を裁判所に伝えるための文書や口頭での声明)を裁判で提出したというニュースがありました。亡くなった人をAIで「復活」させることの倫理についてどう考えるべきか、難しい話ですよね。
※上記を伝えるCNNの記事
He was killed in a road rage incident. His family used AI to bring him to the courtroom to address his killer
この話を調べている中で「Techno-Spiritualism」という言葉を知りました。一言で言えばテクノロジーを使った精神世界とのつながりの模索や実践のことです。実はエジソンとかも結構本気で死後の世界との交信について研究をしていたらしいんですよね。
シリコンバレー文化の源泉にはヒッピーカルチャーがあるなんていう話も聞きますし、テックとスピリチュアリティの関連性は今後話題になっていきそうなイシューの一つですよね。
そうなんですよ。「せかよく」を書いててあらためて気づかされたけど、本当に情報過多な世の中だなって(笑)。対人関係にまつわること、世界経済にまつわること。でもどこかで何かがいろいろ繋がっていて。価値観は常に変わり続けるし、個人、社会、文化は呼応し合って、影響を与え合っているんだと感じますね。
最後に英語学習者が読むメディアとして、英語学習についてお聞きしたいと思います。日本人は義務教育で第二言語として英語を学習していますが、なかなかそれだけで使いこなせるようにならないというのが現状です。
私は日本の学校に行ったことがなくて、漫画とかドラマとかの影響でずっと憧れがあったんですよ。体育館の裏に呼び出されて告白とか(笑)。それは置いておいて、教科書とかを見ると、日本では英語はやっぱり「勉強」なんだなって印象はありますね。一つ記憶に残っていることがあります。私はニュージーランドでも中1まで日本の通信講座を受けていたんですね。当然英語の教科もあって、そのとき「I am a girl.」と書くところがあって、「余裕余裕〜♪」と思いながら書いて提出したんですが、戻ってきた答案を見たら、大文字の「I」(アイ)の、上下の横線を書いていなかったから1点減点されて99点だったんですよ!小文字の「l」(エル)と間違えるからなんですかね。なんか融通きかないなあと。「正解が一つしかない」という教育しか受けていないと、間違えたら恥ずかしいとか、怖いとかが先立ってしまって、英語もなかなか伸びないのかもしれませんね。
英語が流暢な北欧出身の友人の話を聞くと「テレビとか映画やネットで英語を覚えた」って言っていて。日本はどうなんだろうって思った時に、日本はコンテンツが発達しまくってるから、 海外ドラマは吹き替えされているし、日本独自の面白いエンタメもいっぱいあるし、別に英語なんてなくても生きられるっていう環境ではありますよね・・・。日本のコンテンツの素晴らしさは世界から賞賛されています。一方で「カルチャーの自給自足」で十分成り立っているのもあって、世界の動向を主体的に取りに行かなくてもいいという環境になっているのかもしれません。
そういう「英語なんていらないんじゃないか」という環境の中で、本来英語を学ぶということは、どういうことなのか、英語を学ぶことがその人の中にどういう変化を及ぼすとお考えですか。
英語が話せると「新しい視点」が手に入る・・・、と言いたいところなんですが(笑)。よく「英語が喋れていいですね」とか「英語が喋れるようになりたいです」って言われることがありますが、「どうして英語を喋りたいんですか?」って尋ねたくなる気持ちはあります。究極、英語がわからなくても、さっきの震災取材の話じゃないですけど、言語が違うもの同士でも、心を通わせることができますしね。
「何を話すか」の方がよほど重要ということですね。
はい。「せかよく」にもいろいろと書きましたが、世界中で環境破壊が起きている、人権侵害が起きている、というファクトをまずフラットな状態で知ることが大事だと思います。もちろんそれら全てを「自分ごと」にする必要はないと思いますが、自分が関心を持った事柄をいくつかいろんな人々と話す中ではじめて「新しい視点」が手に入ると思っています。その過程でいろんな意見が出てきます。そんなとき、「あなたはそういう立場で物事を見てるんですね。私は、こういう立場で物事を見てます」って、人との違いを認め合う。他者と自分の違いを認め合うために「英語」とセットで「自己表現」をするスキルを身につけることで、世界は広がっていくんだと思います。「私はこう思うけど、あなたはどう思う?」って。

ニキさんから英語学習者の皆さんへのメッセージ