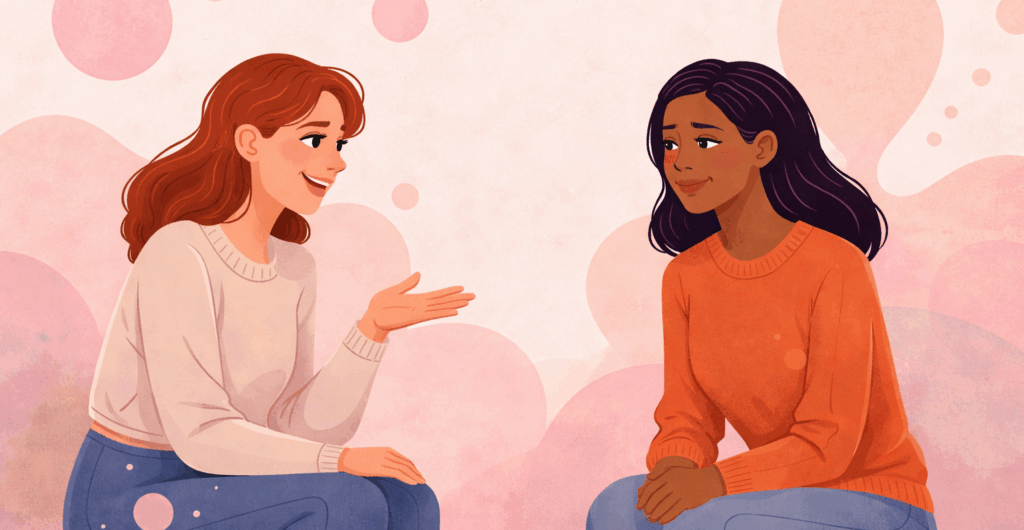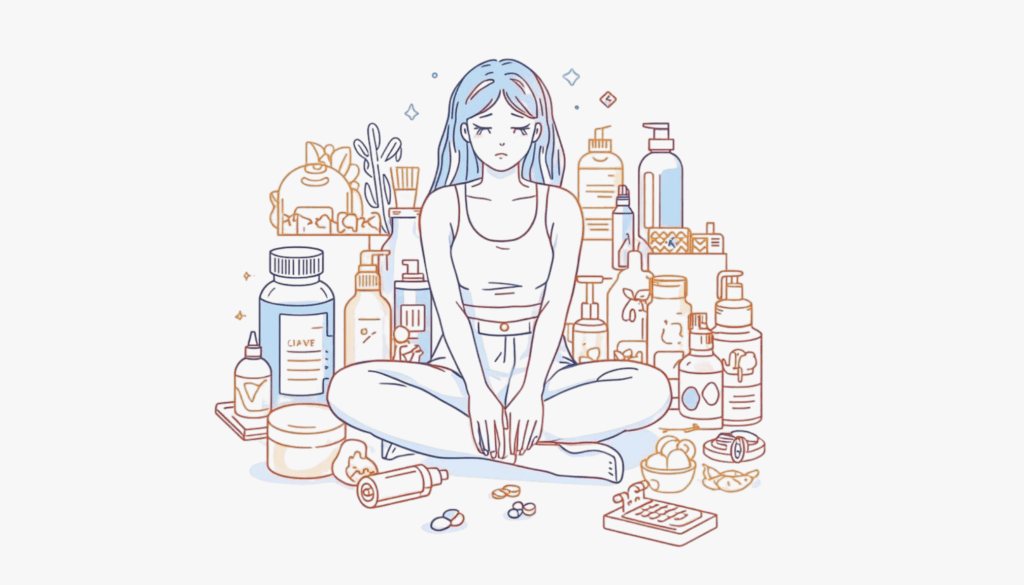日本の学習空間の進化:「ファミレス」から「勉強カフェ」へ
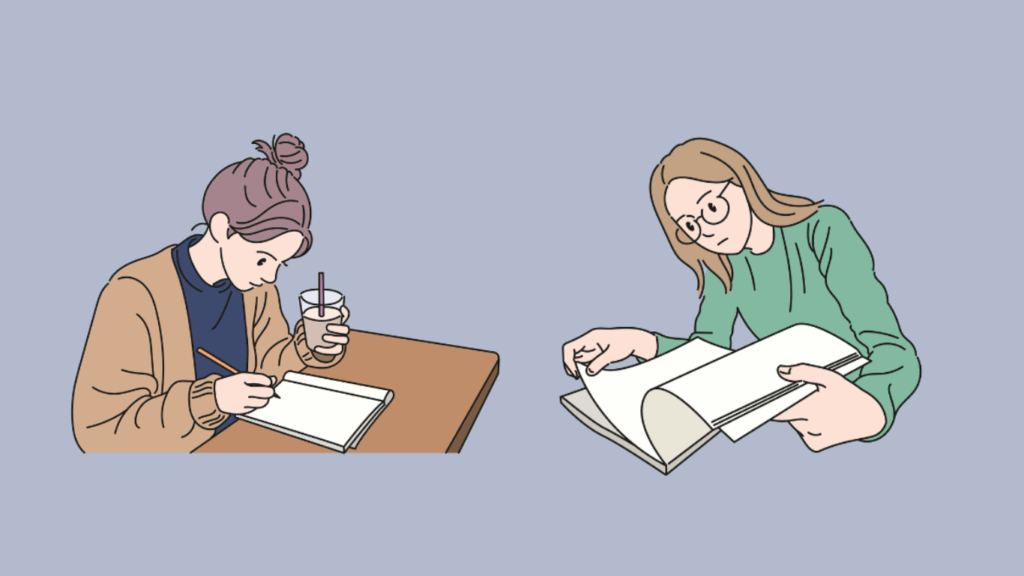
翻訳:POLYGLOTS magazine編集部
今年の初め、エミは英検を控えていました。家ではエミのほかに4人の家族が出入りしていて、集中するのは不可能でした。彼女は毎朝、午前7時の開店直後にファミリーレストランへ行きました。いつものトーストとゆで卵を食べた後、机いっぱいに本を広げ、iPadを開き、リスニング・リーディング・ライティングの勉強ルーティンを始めました。約4時間、できる限り勉強しました。幸い、自分のインターネット接続があり、作業中にコーヒーをおかわりすることもできました。ただし、ほかの客が近くに座っていたため、スピーキング練習は黙って行うしかありませんでした。
時間が経つにつれ、レストランにはさらに多くの人が入りました。やがて入口近くで待つ客も現れました。エミは胸のあたりがぎゅっと締めつけられるように感じました。席を誰かに譲るべきでしょうか?誰も何も言いませんでしたが、彼女はいつも「許されてはいるが、本当に歓迎されているわけではない」と感じていました。
夕方になると、エミは勉強カフェに行きました。これはまったく違う体験でした。カフェには安定したインターネット、たくさんの充電ポイント、長時間勉強するのに適した椅子がありました。さらに、調整可能な照明、半個室のブース、長い共有テーブルが理想的な環境を作り出していました。飲み物を飲み終えても、エミは出て行かなければならないという圧力をまったく感じませんでした。勉強カフェでは、単に「容認されている」のではなく、「歓迎されている」と感じました。
環境スキャニング
ビジネスの世界では「環境スキャニング」という重要な考えがあります。それは、ビジネスに影響を与える可能性のある動向・行動・兆候を観察し分析することを意味します。20年以上日本に住む外国人居住者は、かつて英語メニューのあるレストランを見つけるのがどれほど難しかったかを覚えているかもしれません。観光客や長期滞在者など、さまざまな国の人々が日本に増えるにつれ、レストランは英語メニューを提供するよう適応されていきました。同じように、多くのカフェやレストランは、人々が食べたり飲んだりするだけでなく、勉強や仕事をしに来ていることに気づきました。その結果、インターネット接続や充電設備を追加する店もあります。
学ぶ人・働く人が集まる場所
日本の大都市では、アパートはしばしばとても狭いです。多くの高校生や大学生は、静かで集中できる雰囲気、手頃なドリンク、インターネット接続を保てる環境を求めて、カフェで勉強することを好みます。近年では、フリーランサーやスタートアップの社員、会社員も、勉強カフェ勉強カフェを集中する場として見出し、利用するようになっています。自宅以外で集中したり、オンライン会議に参加したり、個人のプロジェクトに取り組むための場所として活用しているのです。
カフェ側にメリットはあるのか?
一部の客は「どうしてカフェは1杯だけで何時間も座らせてくれるのだろう」と疑問に思うかもしれません。席が空いている時はコーヒー1杯でもありがたい利益になります。また、客が中にいることで店は魅力的に見えます。人々はガラガラに見える店よりも、すでに客がいる店に入りやすいのです。もう一つ重要なのが「リピート客」です。1杯のコーヒーは大したことがなくても、同じ客が繰り返し来れば積み重ねになります。常連客は友人や家族に店を勧めることもあり、それは無料の広告になります。
許される空間から、迎え入れる空間へ
エミが体験したファミリーレストランと勉強カフェの違いは、現代日本の二つの側面を示しています。一方では「容認されている」と感じ、もう一方では「歓迎されている」と感じました。どちらも時代の空気を反映しています。日本は変化する新しいライフスタイルに適応し、勉強カフェは流行を超えて日常の一部になりつつあります。
emoji_objects本記事のイチオシ!フレーズ
(不安や緊張で)胃が締めつけられるように感じる
比喩的な表現で、強い不安や緊張を「お腹に結び目ができたように感じる」と表すイディオムです。試験や発表の前、大事な知らせを待っているときなど、心配や緊張で落ち着かない状態を描写するのに使われます。