「英語社会」で、多言語を生きる 〜通訳・翻訳家の心と身体〜
平野暁人インタビュー(2/3)

進行・構成:POLYGLOTS magazine編集部 写真:Coco Taniya
身体を通して、響き合う音を訳す
翻訳のお仕事についてもお聞きしたいと思います。平野さんの最新の訳書『純粋な人間たち』*を読ませていただきました。この作品の登場人物は主にフランス語話者(セネガル人)ですが、途中で英語を話す人物が登場します。その人物のセリフの上に英語でルビが振られていたり、この本には翻訳的「仕掛け」が散りばめられているなと感じました。
英語でルビを振るというのは、僕の発案ですね。もともと原文では、英語の発言の部分は英語だけだったんです。フランス語訳や注釈がついていなかった。つまり「わからない人はわからないなりに読め」というメッセージなんですよね。
それで、英語のままにすることも考えたんですよ。でも、フランスの読者にとっての英語と、アルファベットすら共有していない日本の読者にとっての英語では、同じ英語でも言語的な距離感がぜんぜん違う。そこを考慮して、やっぱり日本語に訳したうえで英語でルビを振ろう、と決めたんです。

原文で読まれたときと日本語で読まれたときの体験を、同じにする必要があると考えていますか?
翻訳家の中には「訳者は作者代理ではなく、読者代表」だと考えて、一番原文に近い読書体験を提供するためにまずは自分を消す、可能なかぎり透明にする、みたいに心がけて訳している人もいますよね。もちろんそれはそれでひとつの考え方ですから尊重します。でも僕個人は、「それは無理じゃん」って思ってて。だから違うやり方をしています。自分はまず、元の文章をとにかく音読するんです。取り憑かれたように何十回も音読していると、そのうちなんとなく訳が出てくる。
通訳している時もそれに近い現象があって。アーティストがしゃべっている言葉の上に、うっすらと層のようになって日本語で意味が聞こえることがあるんです。そこまで明確に日本語で聞こえるわけじゃないけれど、同時に二つの言語のラインが流れているような感覚。
翻訳している時も、たくさん音読して身体の中に入れていく。そうするとおのずと、その言葉の音が連れてくる日本語があるんですよね。なんというか、多分、フランス語を音で鳴らすことによって、自分の中に堆積している日本語の感覚の中でそれと響き合うものが這い出てくるというか、連れてこられるんだと思うんです。アルファベットというのはあくまで音符であって、本は楽譜ですからね。採譜して閉じ込めた音符に音を還してやることでしか感じ取れないものがある。
ということは、やはり平野さんというフィルターを通して、主観的なものがたっぷり入った訳になるということですよね。
それは絶対そうですよね。本当に、自分が訳したものって、自分の訳したものでしかないと思います。多分、翻訳にもいろんな方法があって、僕の場合は身体に入れていくと、原文のもつ詩性の濃さとか、構成の複層性とか、そういうものがおのずと訳文になって出てくるんだと思います。
「音読」という身体を通しての翻訳が平野さん流翻訳だとして、一方、現在主流にあるのは「自分を消す、可能なかぎり透明にする」翻訳なのでしょうか。
僕は誰にも翻訳を教わったことがないし、規範みたいなものがあったとしても気にしたことがないのでよくわからないけれど、たまに同業の人と接すると、なんかちょっと苛立たれてるな、と感じることもありますね。「なんでお前だけそんな自由にやってんだ」みたいな。
「ここは普通こう訳すのでは」みたいに言われることもあるし、「平野さんの主観が入りすぎでは」と言われることもある。でも、そういう意見はあまり理解できないんですよね。昔から「おまえの『普通』に用はない」と思って生きてきたし、僕が訳す以上は僕の主観が入ってナンボだし、僕が主観で訳すからこそ僕ならではの素晴らしい訳文が生まれるので……「僕、僕」って我ながらうるさいな。すいません。
すごくよく勉強して文法に通じている人であれば、それなりに「正確」な和訳を作ることはできるけれど、「正確な和訳」と「質の高い翻訳」の間には、きわめて大きな隔たりがあります。だから翻訳は難しいんです。
翻訳ってやっぱり「無理」を通しているところがあるんですよね。特にフランス語から日本語にするとか、英語から日本語にするとかっていう時の負荷は、フランス語からイタリア語にする時よりもずっと高いわけです。言語の面でも文化の面でも距離感がまったく違う。だから実際、世の中に出てる日本語の翻訳で、全然うまくいっていないものはたくさんある。
それに翻訳を読むって、すごく疲れることでもありますよね。言葉の面だけじゃなくて、人名とか地名とか設定とか時代とか慣習とか、自分の慣れ親しんだ環境からはすごく遠いものをいちいちがんばってインストールしながら読まないと読めない。すくなくとも僕はそう。それなら最初から日本語で書かれたものを読んだ方が楽、という思いもあります。実際、僕はこの仕事をしていながら海外文学ぜんぜん読まないんですよ。フランス文学でさえ、スタンダールもバルザックもゾラもフローベールもプルーストもデュラスも大学の授業以外で読んだことがない。そもそも興味がない。『星の王子様』は読んだことあるけど大っ嫌い。ついでに言うとゴダールも観たことがない。おそらく日本でいちばん海外文学を読んでいない文芸翻訳家だと思う。
でも、これがまた辛いところでもあるんですが、原書に力があると、翻訳の良し悪しにかかわらずちゃんと人に届くんですよね。もちろんそれは文学にとってはいいことです。作品それ自体の力が表現の巧拙を超えて伝わるわけだから。一方、翻訳という観点からすると、「翻訳って所詮翻訳だな」と。「へたくそが訳したって名作は名作だしな」って。訳した本が売れたというだけで、訳した人まで名翻訳家であるかのように扱われることもありますしね。だから、「翻訳研究」とか、翻訳を特別なもの、訳すという行為自体をなにか魔術的な営みとして語る、ありがたがる、みたいなのは個人的にはあんまり好きじゃないんです。こういうこと言うとすごく怒る人がいそうだけど。はっはっは。
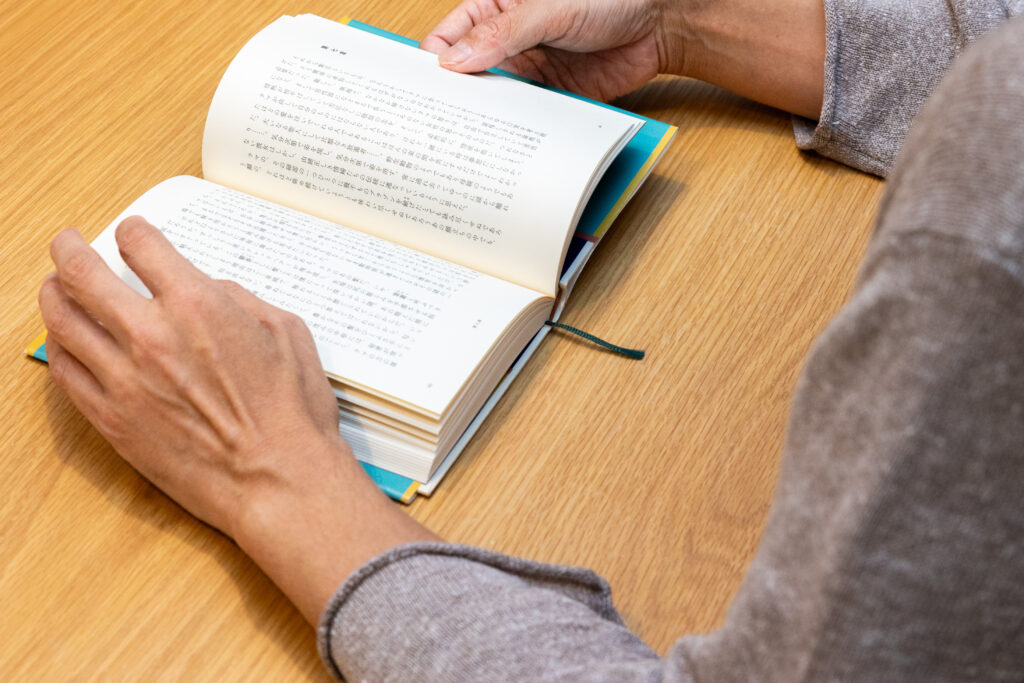
多言語のあいだで揺れ動く、自分の中の他者
「日本語で書かれたものを読んだ方が楽」とおっしゃいましたが、最近日本では、海を越えた場所で生まれた作品への関心が薄れてきているようにも感じます。洋楽や翻訳文学などの需要が減っているとも言われますが、そこについてどう思われていますか?
僕が学生のころはまだ「たくさん本を読んでいる=頭が良い」という価値観を素直に信じている人がたくさんいたように思います。それも「西洋の文物」にだいぶ偏っていた。まあ僕がフランス文学科だったというのも大きいと思いますが。
僕自身は「本物の文学や芸術、進んだ知識や意識は欧米から来る」みたいな西欧中心主義的な価値観に支配されたインテリたちを幼いころから身近にたくさん見てきて(そんなわけねえだろ)と思っていました。僕は本も読むけど、漫画も大好きだし、高校をサボって寄席に行ったりとか。プロレスなんて後楽園ホールに週1で通っていた時期もあったし。とりわけ博士課程に進んでからは学力と知識の鬼みたいな友人たちに囲まれていましたけど、他人は他人だし。各々が自由に「自分の教養」を育てていけばいい、と思っていたんですよね。文化相対主義的な。教養相対主義。
でも最近、「教養≒権威」みたいな価値観を頭ごなしに嫌悪する人がずいぶん増えた気がする。誰も大事にしなくなってきたというか、知らないものを知ろうとする努力をしないまま否定する、丸腰の自分にわからないものはすなわち価値がない、みたいに即断する傾向が加速している感じがして、その延長線上に「洋楽や翻訳文学≒遠いもの」への関心の低下もあるのだとすると、それはそれでよくないと思うんです。だから僕みたいに「外れ値」の人間も、かつては「教養としての読書? 古典? まあそっちはそっちで大事になさったらよろしいのでは」くらいの距離感でいられたのが、そう呑気なことも言っていられなくなってきた。
いや、僕もぜんぜん読まないんだけど、「あっちはあっちで価値があるんだろうけど自分はいいや」というのと「知らんけど遠いしどうでもいいし無価値だ」と即断するのとはまったく違うと思うんですよ。敬意の有無ですね。「読書量で人間の価値は決まらねえだろ!」という反発は「大量に読書して知識や感性を涵養する」という営みを遂行している人たちに対する敬意の裏返しでもあるわけで、そこには憧れすら潜んでいたりする。「あの人たちは自分の知らないことをたくさん知ってるんだな、かっこいいな」みたいな。コンテンポラリーアートを見て「意味がわからん! まやかしだ!」と言下に否定せずに「これがわかるってどんな気分だろう」「これに夢中になるのはどういう人なんだろう」と想像しながら途方に暮れる……これも僕自身の話なんですけど。
あ、もっと言うと、パチンコとかでも同じですよ。僕は大きな音のする閉鎖空間がものすごく苦手なのでパチンコ屋さんの前を通るだけでもつらいけど、だからといってパチンコが無価値なものなのかどうかはわからない。やったことないから。「依存性の高い非生産的なゲームでしょ」と切り捨てるのは簡単だけど、適度に楽しんでいる人だっていくらでもいますよね。だから、自分は興味がないからやらないけど、お店に足を踏み入れたことすらない以上は、真価についてのジャッジは保留します。
とにかく、知らないものをただ否定したり、わからないものを無闇に蔑んだりするのはあまりに寂しい。自分と無縁に感じられる「遠いもの」であっても敬意をもって眺めたい。たまにはうっかり触ったりしてみたい。
映画なんかにしても、20年くらい前までは「どこの映画館行っても外国映画ばかり。もっと邦画を見せてくれ」と思っていたのに、今は『鬼滅』と『国宝』しかやっていないような状況すら生まれてしまう。いや僕も『鬼滅』は連載時に衝撃を受けて夢中で読みましたしいろいろ語れますけど、「さすがにそれだけでいいのかな」とは感じますよね、やっぱり。
そういう面では、無視できないレベルで状況が変わってきているなという気がしています。
国内の表現や作品だけで満足し始めると、同質性の高い集団の内部で関心のベクトルが飽和することで「他者への無関心」も進行するのでは、という危機感がある。その一方でTikTok的なもので一瞬で世界の裏側まで行けるから、「もう知ってる」気にもなれてしまう。しかも海外といっても欧米、あと今だったら韓国とか、イメージが情報として支配的に消費されている特定の地域をざっくり「海外」と呼んでしまったり。
「他者への関心」についてですが、以前、平野さんは「翻訳とは自分の中の他者と向き合う行為だ」とおっしゃっていました。翻訳という行為を繰り返して見えた「平野さんの中の他者」とはどんなものですか?
翻訳や通訳を通して「他者」や「自分の中の他者性」とどう向き合うかというのは、いろんな角度から考えられるテーマですよね。
まず、異言語に浸ることで自分のそれまでの人格や振る舞いがどのくらい影響を受けるか、という緊張関係が常にあります。「言語が人間の在り方のどこをどんなふうに規定しているのか」が実感できるようになってくる。たとえばフランス語では「良い」ことを「悪くないね」と表現することが非常に多いんですね。「せ・びあん!(C’est bien! /いいね!)」と言えばいいのに「ぱ・まる!(Pas mal !/悪くないね!)」とまず否定形で入る。「まじでぜんっぜん悪くなかった!(Franchement c’était pas mal du tout!)」とか言うんですよ。いや、もちろんそれは翻訳するなら「めっちゃよかった!」なんですけど、じゃあ素直にそう言えよ!と。でも、それもまた面白味です。言語表現にフランス的な精神性が宿っているわけですね。
で、フランスに住んでどっぷりフランス語に浸かって生活している人の中には日本語でもそういう、フランス的な構文で喋るようになる人が少なくないし、そうするとなにげないジェスチャーや表情筋の使い方まで変わってくる。肩をすくめて「さあね」とか、本当にし始める。昔の僕はそれがすごく嫌で、ただただ「ダサい」と思っていましたね。
今思えば、それは単にその様子が滑稽にみえるということだけじゃなくて、そういうふうに振る舞う人々の多くを蝕んでいる「ヨーロッパ的になること=洗練されること」という選民意識、「我こそは脱亜入欧レースの勝者」みたいな顔つきが嫌だったんだと思います。「日本人ってダメだよね」「フランス人はそういうことしない」「ヨーロッパでそんなことしたら笑われるよ」みたいないわゆる「出羽守*」的な、嘲笑にも似た感覚を内面化したくなかった。
翻って、言語それ自体がひとつの思考体系である以上、どの言語で思考するかによって導き出されるものも変わってくる。表現はもちろん、内容も変わりうる。この前も、ある作家にフランス語でメールを書き始めたらいつのまにか詠嘆調の散文詩みたいなものが出来上がって、えっいま俺こんな感じだったんだ!とびっくりしました。もとい、「書く」という行為は常に「書かれたものを眺めて自分を発見する」という、ある意味で自己の他者性に強く依拠した営為ではあるのですが、何語で書くかで出てくるものは確実に変わる。同じ自分のどこかに「フランス語で表現する自分」という他者が潜在しているわけです。
特定の言語を深く身体化しようとすればするほど、どうしても侵食される部分は出てくる。通訳や翻訳を通していろんな人と出会って、さまざまな文化や言語に触れていくうちに、価値観も状況判断も語彙の使い方も変わっていく。そこにはせめぎ合いもある。でも同時に、そのせめぎ合いを通して「他者性とはどこにあるのか」「何が自己を規定しているのか」という問いが絶え間なく立ち上がるし、それが魅力でもあると思います。




