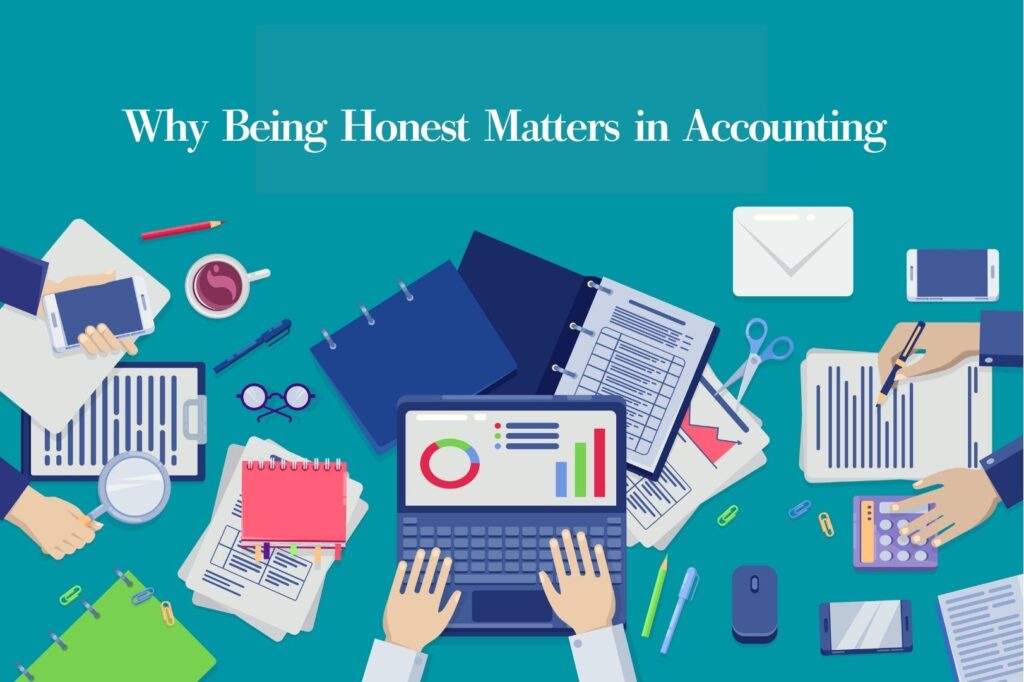日本の職場における従業員のウェルビーイング

英文記事執筆:Everett Ofori / 翻訳:POLYGLOTS magazine編集部
どの会社も、健康で、最善を尽くす用意のある従業員を求めています。
しかし、従業員は機械ではなく人間です。ときには、人は疲れた状態で、あるいは家庭や職場の問題を心配しながら出勤します。こうした不安は、集中したり良い成果を上げたりすることを難しくする可能性があります。
日本では、労働者のウェルビーイングは、ますます重要になっています。雇用者、政府、そして社会のすべてが、この問題に注意を向けています。日本の企業における従業員のウェルビーイングに影響する三つの主要な力―規則の順守、従業員の健康支援、前向きな職場文化の構築―を見ていきましょう。
規則の順守
2015年以降、日本の法律は、従業員が50人以上の企業に対し、年1回の「ストレスチェック」の実施を義務づけています。この検査は、心理社会的ストレスに関する短いアンケートです。
心理社会的( psychosocial )という語には二つの要素があります:
・psycho は、思考、感情、ストレス、そしてパーソナリティを意味します。
・social は、家族、仕事、文化、そして社会を意味します。
たとえば、心理社会的問題とは、同僚との関係不良によって生じるストレスのことと言えます。
2015年12月に開始されたストレスチェック制度には、三つの目標があります:
1. 調査とフィードバックを通じて、労働者が自分自身のストレスを理解するのを助けること
2. 集団の結果を参照し、ストレス要因を減らすことで、職場環境を改善すること
3. ハイリスクの労働者を見つけ、早期に医師へつなぐこと
ある従業員のストレスが高水準にあると判断した場合、医師は精密検査を勧告できます。従業員が同意すれば、会社はこの評価の費用を負担しなければなりません。
従業員のウェルビーイングに配慮しないと、高い代償を払うことになる可能性があります。
企業は法的問題に直面し、金銭を失い、評判を損なうかもしれません。日本で職場ストレスがどれほど深刻になりうるかは訴訟が証明しています。だからこそ、規則の順守が非常に重要なのです。
従業員の健康支援
多くの日本企業は今、従業員の健康を維持することが人にもビジネスにも良いことであると認識しています。健康で幸せな従業員は、より良く仕事をこなし、目標を達成することができます。
一方で、従業員がストレスを感じたり、うつ状態になったり、病気になったりすると、多くの休暇を取ることがあります。この欠勤(absenteeism)は、仕事の進行を遅らせ、生産性を低下させます。これを防ぐために、企業はカウンセリングサービス、ストレス管理のワークショップ、そして従業員が経験を共有できるサポートグループなど、より多くの支援を提供しています。
前向きな職場文化の構築
従業員のウェルビーイングは、法令遵守やコスト削減だけに関することではありません。それはまた、人々が尊重され、価値を感じられる職場をつくることにも関わっています。
企業が従業員を大切にしていることを示すと、従業員は意欲を感じ、最善を尽くそうとする姿勢が高まります。また、従業員は雇用主をより信頼するようになり、これがスタッフと経営陣の関係を強化します。
241の加盟企業を代表している全国銀行協会は、2015年に国連の持続可能な開発目標(SDGs)を採択しました。同協会は、テレワーク、転勤範囲の制限、個人の特性や希望に基づくキャリア形成の促進といった選択肢を提供することで、育児やワークライフバランスに適した職場環境の整備を目指しています。それがより良いチームワーク、より高い士気、より強い企業パフォーマンスへとつながります。
ウェルビーイング:競争上の優位性
組織は競争力を保つために互いに学び合います。
従業員が、自身のウェルビーイングを優先する組織を好む傾向を示すようになるにつれて、より多くの企業がサウスウエスト航空の共同創業者ハーブ・ケレハーの言葉に耳を傾けるようになるでしょう。
彼はこう述べました―「従業員を第一に考えなさい。従業員を大切にすれば、彼らは顧客を大切にし、顧客はまた戻ってくるのです。」
menu_book参考文献
emoji_objects本記事のイチオシ!フレーズ
欠勤(の多さ)/常習的な欠勤
The company introduced a wellness program to reduce employee absenteeism. (その会社は従業員の欠勤を減らすために健康促進プログラムを導入しました。) 「absenteeism」は「absent(欠席している)」の名詞形ですが、 単に「欠席」ではなく、習慣的・慢性的な欠勤や欠席の傾向を指します。 特にビジネスや教育の文脈で、「健康問題やモチベーションの低下による欠勤の多さ」を表す語として使われます。