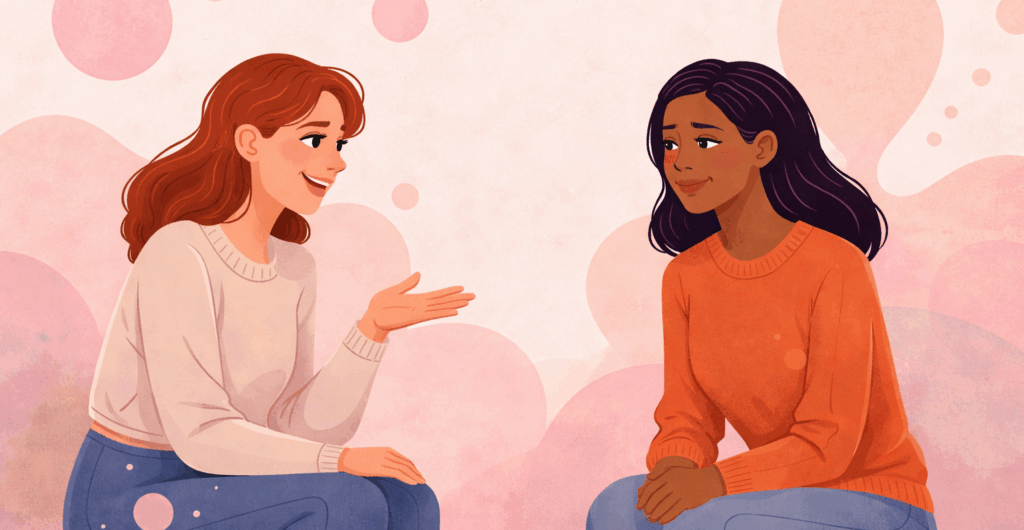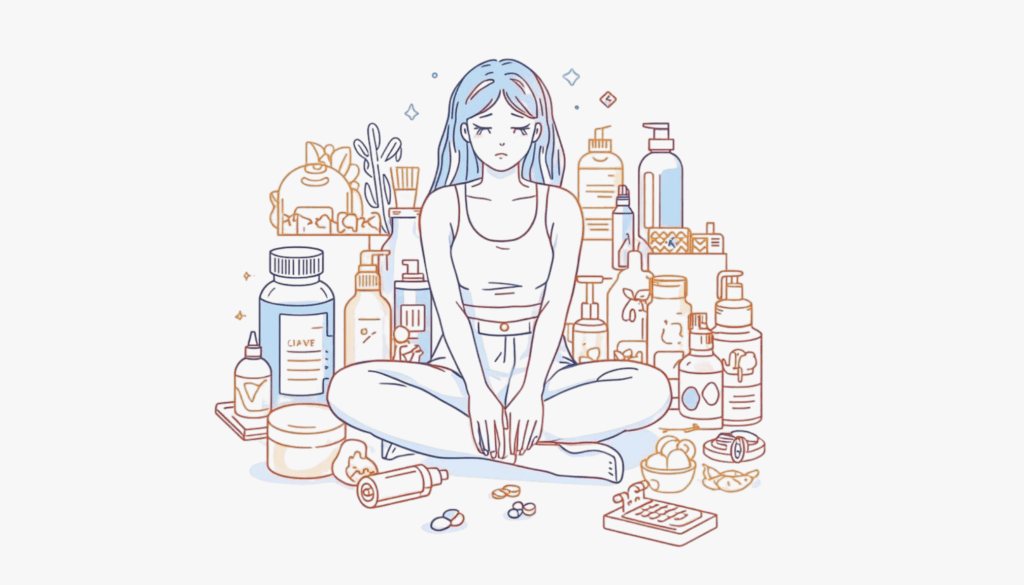「ギャップイヤー」の流行:日本の若者の間で高まる関心

翻訳:POLYGLOTS magazine編集部
日本では、中学生や高校生が放課後に塾へ通うことは一般的です。中には1日に3時間から8時間勉強する生徒もいます。彼らの目標は入学試験に合格し、よい大学に進学することです。こうしたプレッシャーの中にいる若者がもっと自由を夢見ることを誰が責められるでしょう。その夢の形の一つが、ギャップイヤーです。
メリアム・ウェブスター辞典によれば、ギャップイヤーとは「学業を離れて非学問的な活動を行うための1年間の休止期間」と定義されています。しかし日本におけるギャップイヤーは必ずしも同じではありません。学業の立て直しのためのものもあれば、探求や充実のためのものもあります。
「浪人」のギャップイヤー
すべての学生がギャップイヤーを選ぶわけではありません。希望する大学に合格できず、「浪人」になる人もいます。日本の入試は、共通の全国試験と大学ごとの個別試験の両方を含むのが普通です。成功しなかった学生は多くの場合、その後の1年を授業の復習や補習、そして再挑戦の準備に費やします。
こうした学生は浪人生と呼ばれます。これは「主君を持たない侍」を意味します。主君を失った侍のように、彼らは学校に属さない「さまよう者」と見なされるのです。研究によれば、浪人の経験は幸せなものではなく、ストレスをもたらし、頭痛などの身体症状を引き起こすこともあります。しかし、この1年はまた、過去の失敗から学び、弱点を見つけ、勉強と休息のバランスを取る機会ともなり得ます。幸いなことに、多くの浪人は、確かに大学へと進学しているのです。大抵の場合、その忍耐と努力は最終的に実を結ぶのです。
充実のための自発的なギャップイヤー
別の学生にとっては、事情が異なります。試験に合格しながらも、大学への入学を延期する人もいるのです。彼らはこの1年を使って旅行をしたり、ボランティアやアルバイトをしたり、語学を学んだり、インターンシップで経験を積んだりします。この選択はしばしば、興奮と新しい発見をもたらします。例えば、多くの日本の若者が海外へ旅行します。
オーストラリアは近さ、活気ある都市、美しい自然のおかげで最も人気のある選択肢となっています。さらに英語を実践する機会も豊富です。ニュージーランドもまた人気の行き先です。山々や緑の野原、そして環境保護に重点を置く文化は、アウトドアを愛する人を惹きつけます。そこへ行った学生は、すばらしい思い出と新しいスキルを身につけて帰ってきます。また別の学生は、アメリカやカナダ、あるいはイギリス、ドイツ、フランスといったヨーロッパの国々を好みます。これらの場所は文化の多様性、学術プログラム、そして国際的な仕事の機会を提供してくれます。
計画を立てる
ギャップイヤーはわくわくするものであり、有益でもありますが、注意深い計画が必要です。学生は自分の目標について考え、決断する前に調べるべきです。試験準備、旅行、ボランティア、インターンシップのいずれであっても、支援を提供する団体を見つけることができます。海外に行く場合は、安全と語学力について考慮すべきです。しっかりと準備すれば、ギャップイヤーは安全で実りあるものとなるでしょう。
ニューヨーク大学のスコット・ギャロウェイ教授は、休みを取る考えを強く支持しています。彼はこう言います。「ギャップイヤーは例外ではなく、むしろ標準であるべきです。ギャップイヤーを取った学生の90%は大学に戻り、より高い確率で卒業し、成績も良くなります。」
将来を見据えて
日本の若者の中で、ギャップイヤーの価値を見いだす人が増えています。ある人にとっては、浪人として立ち直り、再挑戦する助けになります。別の人にとっては、旅行や出会い、新しいスキルの発見の機会となります。どちらの場合でも、ギャップイヤーは自己成長への一歩です。しっかりと計画を立てれば、それは大学やその先での成功に向けた準備となるでしょう。
menu_book参考文献
emoji_objects本記事のイチオシ!フレーズ
「志望大学」「行きたい大学」
“desired university” は、「自分が入学を望む大学」という意味で、特に入試や進学の文脈で使われます。 “desired” は「望ましい」「希望する」という形容詞で、目標・志望としての意志を表すフォーマルな語です。